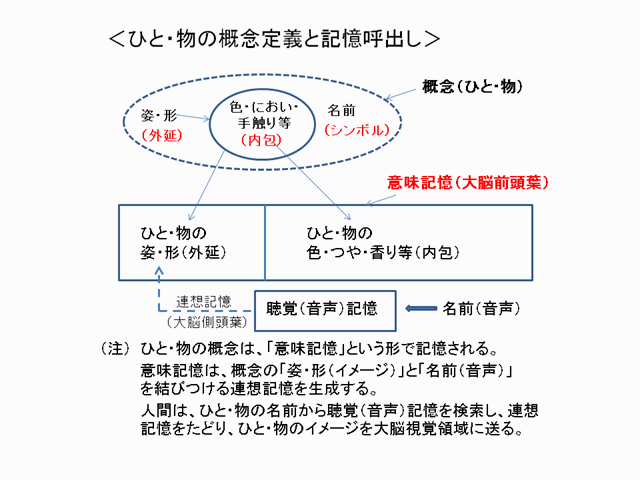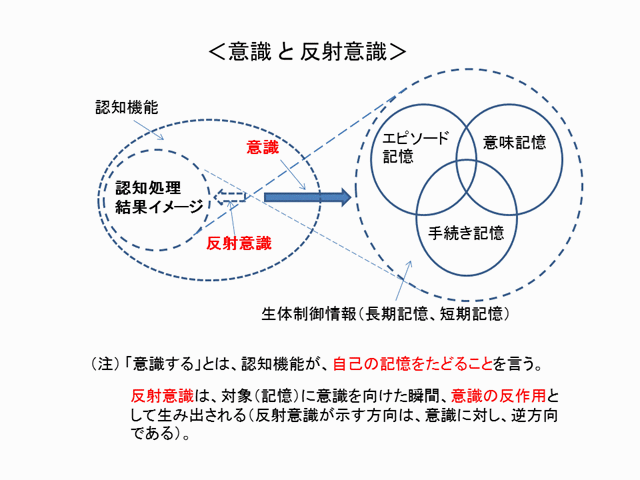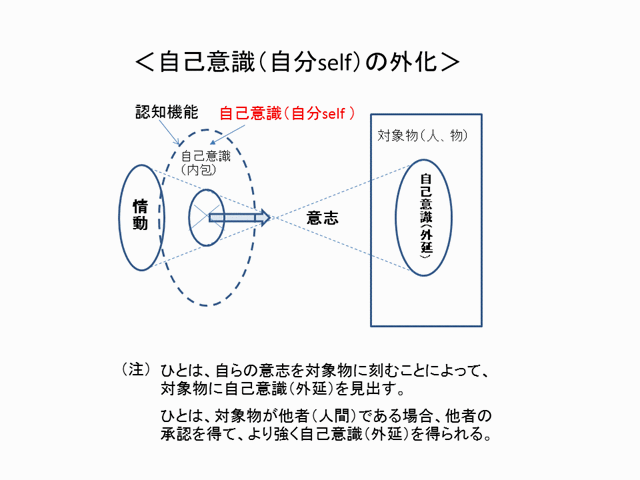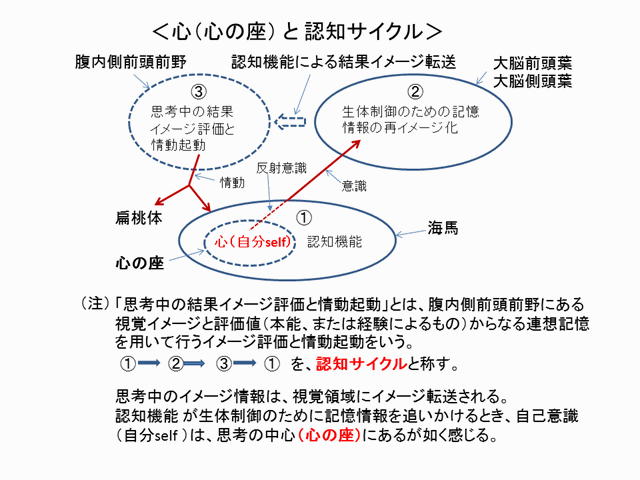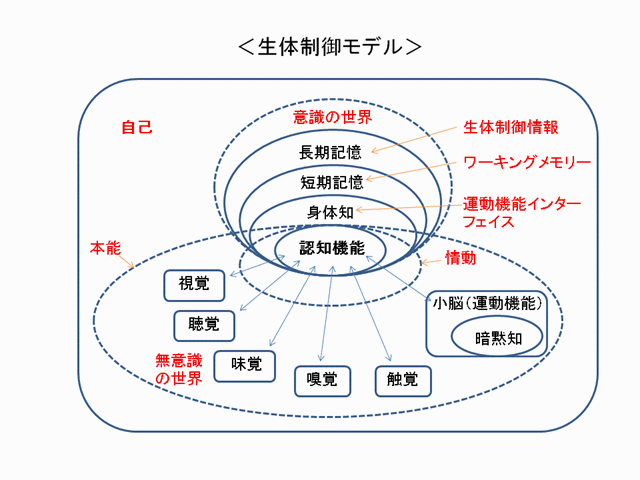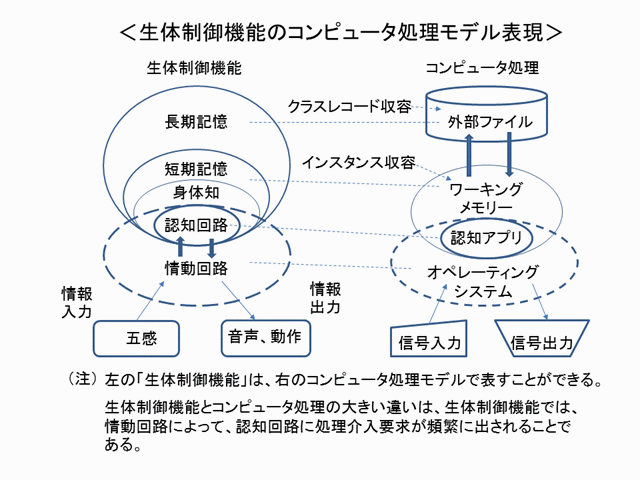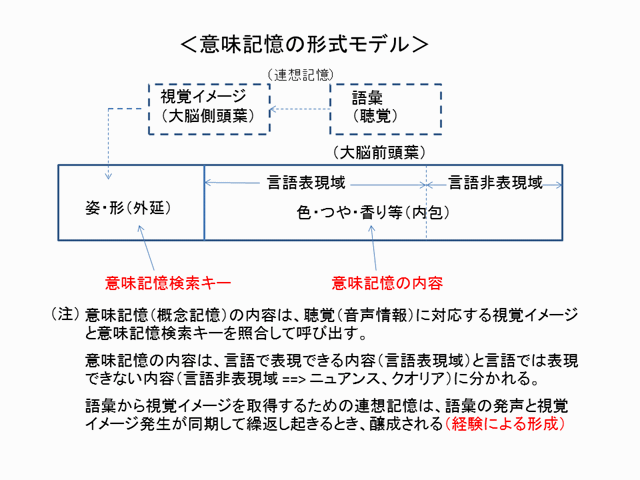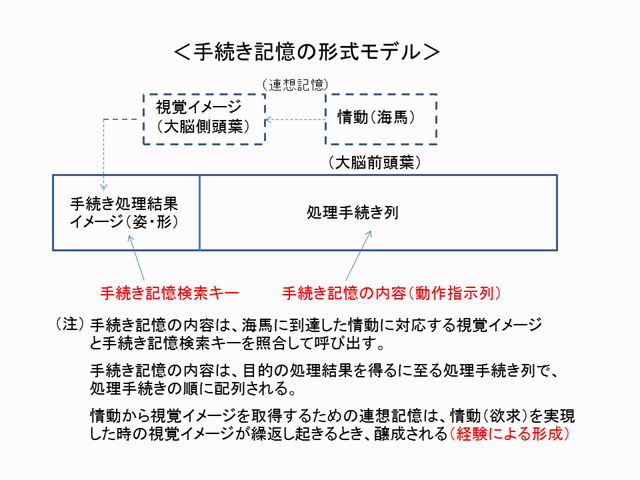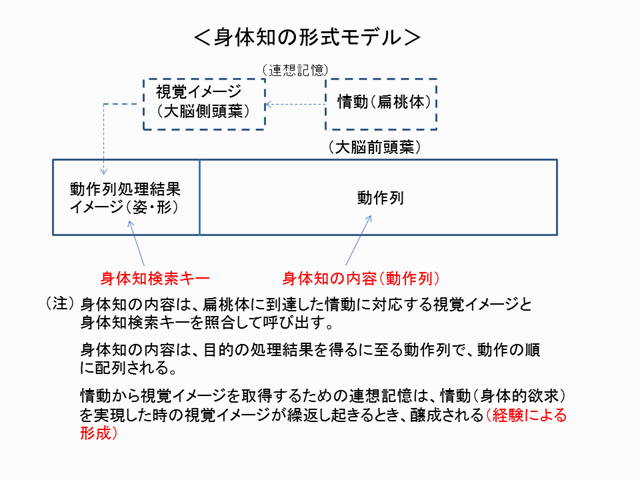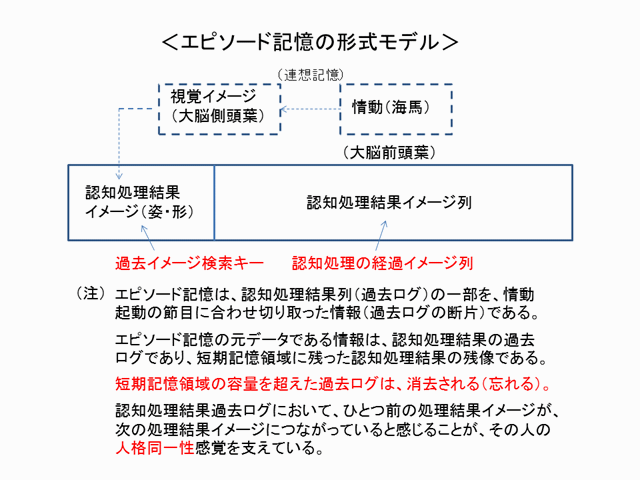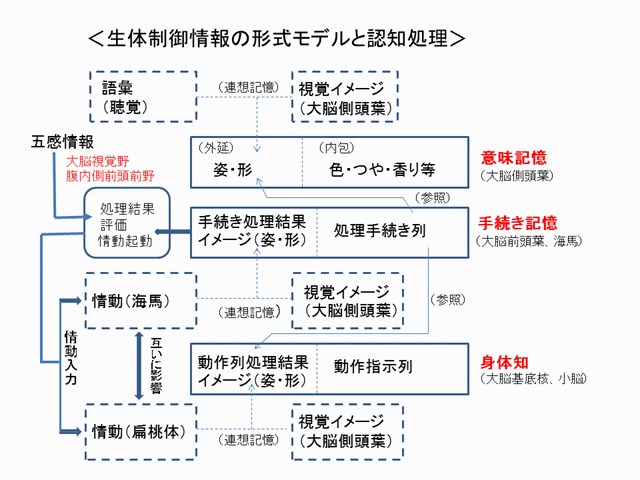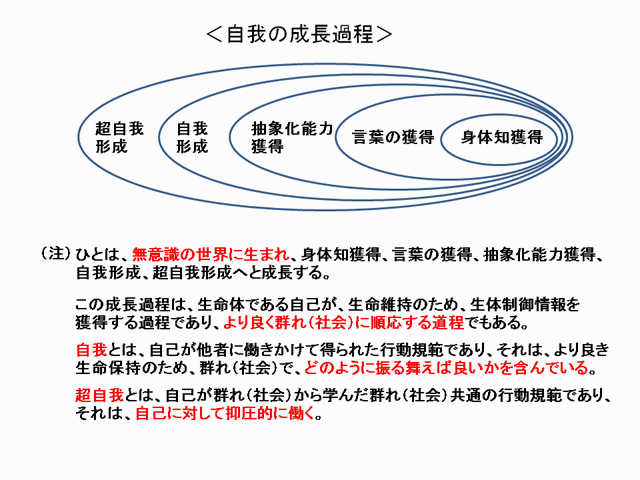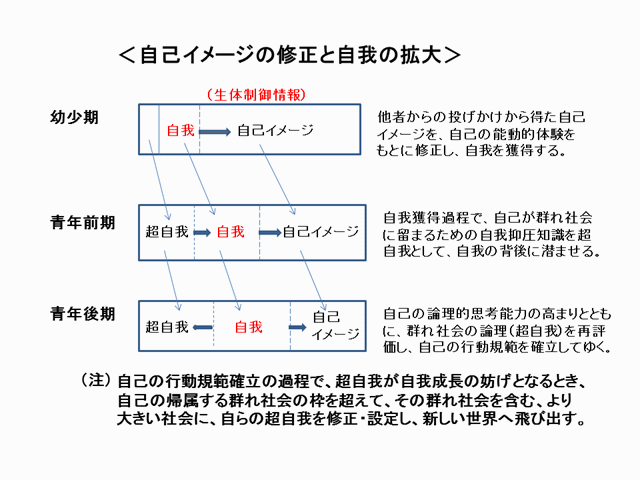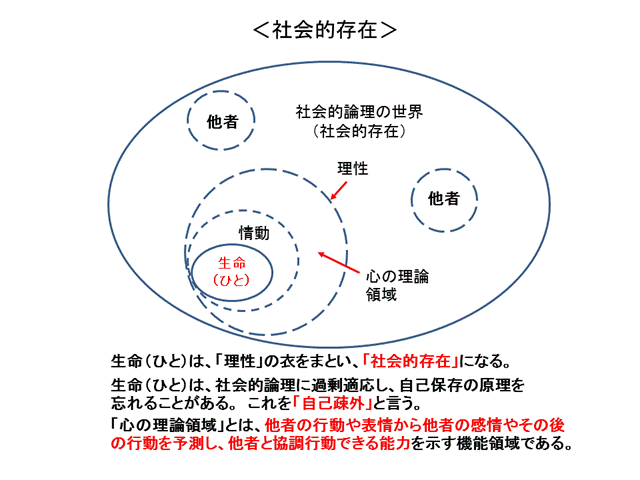心の哲学仮説(トシーマの哲学ノート)
デカルト曰く、
「我思う、故に、我あり」
しかし、これに対し、わたしはこのように考えた。
「我思う、故に、我ありたい」
このように、自己の存在を問うのが、人間の本性ではないか?
現代の「心の哲学」の有様を見るに、「心(心の座)は、どこにあるのか」を求めて、議論百出である。
そこで、筆者も素人ながら、「反射意識」という新しい概念を掲げて、この議論に加わりたいと思う。
「心とは何か」、「心と体の関係」を「心の哲学(トシーマの仮説)」として筆者なりにまとめたものを、ご一読願えれば幸いである。
(目次)
1.はじめに
2.「心」とは、どのようなものであるか(「トシーマの仮説」の基本概念 と 基本テーゼ)
3.人間は、「矛盾した存在」である(生存本能 と 群れ社会帰属)
4.人間は、「矛盾した存在」を、どのように克服しようとしているか(情動 と 認知機能)
5.人間は、動物的本能に加え、新しい能力を身につけた(認知機能と生体制御モデル)
6.人間(個体)は、群れ社会で学んだ知恵(経験)を、どのような形で身体に保持するか(生体制御情報の形式モデル)
7.人間(個体)は、生体制御情報を、どのように活用するか(デカルト以来の心身問題に対する一つの解答)
8.生命(ひと)は、「他者の世界」に生まれ、「ひと」になる(自我の成長、そして「自由」)
9.生命(ひと)は、認知機能(理性)の衣をまとい、社会的存在になる(自己保存と自己疎外)
(注1)記載内容は、予告なしに変更することがあります(最終更新日 2022.10.31)。
(注2)心の哲学における諸課題について、「トシーマの仮説」にもとづく筆者なりの解釈(トシーマの仮説詳論)を、
「心の哲学 -- ひとは、進化の結果手に入れた「心」を、何故に粗末に扱うのか?(あなたに心の補助線を)」
に公開しています。
(注3)メンタルモデル記述用言語に興味のある方は、筆者作成のプログラミング言語
「Lisp M式への回帰(新しいリスト処理言語GavaOne)」
をご参照ください。
1.はじめに
最近の「心の哲学」の解説を読んでいると、いまだデカルトの心身二元論を超えていないように思える。
特に、心と体が相互に作用しあうと言う考え方については、その後の哲学において、数限りなく議論されてきたが、
いまだ、心の存在が明らかにならなければ、先に進めないらしい。
20世紀後半以降の認知科学と大脳生理学の進展で、それまでの哲学的思考の基礎が、大きく変わったにもかかわらずである。
少なくとも、学問の基礎を与える学問としての哲学の役割は、大きく後退したと思っている。
しかし、「哲学には、思想的基礎を与え、より良き人生に貢献する役割がある」と筆者は考えている。
とりわけ、混迷の度を深める現代にあって、「心の哲学」の果たす役割は大きい。
ひとは、生を得て以来、絶えず選択と決断の連続であり、特に思春期以降、より広い社会へこぎ出す若者にとって、
人生の指針となる考え方(哲学)を得ることは、その人のより良い人生を予感させるものとなろう。
しかし、現代の哲学界を見るに、先達の研究業績を解説するのに多くの時間を割いており、
新しい科学的知見を取り入れた若者に訴えかける(革新的な)提案が少ないように、筆者には思える。
最近の認知科学をはじめとする人間に関する研究業績の充実ぶりを見るに、そろそろ新しい哲学の萌芽を見ても良い時期であろう。
哲学と言えば、一部の専門家の学問であるように見えるが、情報通信技術の発達により、
最近では、素人でも参加できる(意見表明できる)状況にあると思う。
そして、学者(哲学者)にない素人の発想が、閉そく感のある既存哲学の世界に、新しい風をもたらす可能性がある。
それは、「ウェゲナーの大陸移動説」が、地学の世界に革命的な転換を与えたようにである。
筆者は、過去50年にわたり、ある考えに囚われてきた。それは、
「哲学は、何故に、心の存在にこだわるのか? それは、学問のためのみか?」
「心の存在を問い続ける姿が、人間の本性ではないか? それは、何のために?」
である。
このノートは、これまでの思索結果を整理するためのものである。
これまでの思索結果をお見せする前に、筆者の基本的態度を明らかにしておく必要があろう。
筆者にとって、「哲学は、現実世界の存在を前提にしなければ、何も始まらない」と言うことである。
すなわち、「自然主義」「進化心理学」を前提としている(「霊魂」の存在を固く信じている方には、
是非読んでいただきたい、仮に、その内容が不都合な真実であってもである)。
そもそも、思索の始まりは、「ゼノンのパラドックス」を知った時からである。
いろいろの解説書をひもとくも、なかなか理解できず、おのれの馬鹿さ加減を思い知らされたのである。
ただ、その結果、得られたものが、その後の思索の原点であるように思う。
そこで得られた信念は、
「物には、姿・形(量的概念)と色・におい・味・触感(質的概念)があり、名前が付いている」
ということである。
そして、新たな次の疑問
「人は、自分自身の存在を、物と同じように捉えるであろうか?」
が湧きだし、ながく霧に包まれることになった。
今までの哲学が、難しい概念を用い、複雑な論理を文章で表現している姿は、素人の入り込む余地などないように思える。
しかし、昨今の認知科学・人工知能技術の発展のお陰で、「心の機能をモデル化する」ことによって、
心のありさまを、哲学独特の概念を用いずに、より分かり易く表現できるのではないか、と感じている。
21世紀に入り、重要な脳科学上の進展を知るとともに、なが〜い長い霧の時期も終りを告げた。
その進展とは、
「視覚情報は、外界の映像が網膜で視覚信号に変換され、視神経で大脳に伝えられた後、映像として再合成されたものである」
「大脳には、視覚情報と音声情報の対応関係などを記憶する複数の連想記憶領域がある」
「大脳には、他人の顔を優先的に見いだせる機能がある」
「ミラーニューロンの発見」
である。
これらの新しい知見は、従来の自意識から始まる考え方に対して、その考え方を180度転換する(無意識から始まる)よう促しているように思える。
本文は、筆者なりの「メンタルモデル(トシーマの仮説)」の構築を目指して悪戦苦闘した結果を、お披露目するものである。
このメンタルモデルに記述してある内容が、過去の文献にあるか否か、
先達の発言にあるか否か、をチェックしていない(充分に配慮しているつもりであるが)ので、
素人のメモ(学術論文ではない)である故として、お許し願いたい。
少しでも、読者のお役に立てば、幸いである。
2.「心」とは、どのようなものであるか(「トシーマの仮説」の基本概念 と 基本テーゼ)
忙しい現代人のために、この仮説の基本概念と基本的考え方(基本テーゼ)を説明する。
(基本テーゼ1)ひとは、幼少期に、「人・物には名前があり、姿・形、色・におい・手触りなどがあること(人・物の存在)」
を知る。
ひとは、「人・物の存在」の認識(「実在する」と思うこと)において、
「姿・形(外延)」と「色、におい、手触りなど(内包)」を切り離して考えることはできない。
このことは、人類が進化の過程で獲得した「叡智」であり、諸科学の原点である(と筆者は考えている)。
基本テーゼ1を、後に述べる記憶形式モデルで表せば、次のとおりとなろう。
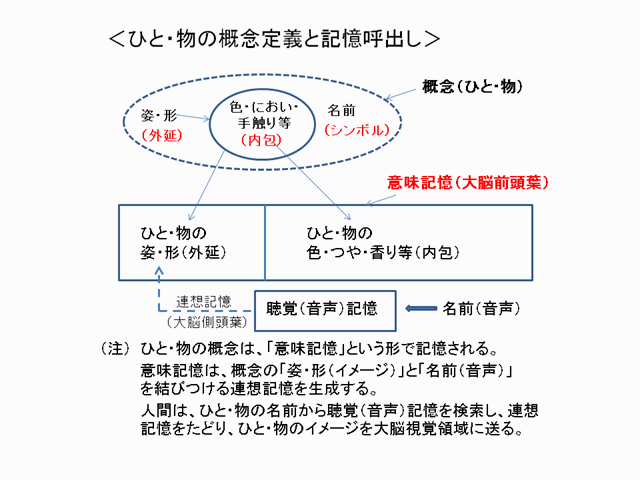
ひとは、自己の存在を、どのように知りうるか。
(基本テーゼ2)ひとは、観察者たる自己を直接見ることはできない(鏡などを用いて、間接的に見る)
ひとは、誕生から幼少期にかけて、他者の働きかけにより、「自分には、名前があり、どのような姿・形を持ち、
どのように他人に接しているか」(自己イメージ)を獲得する。 これで、ひとは、世界内存在となった(と思っている)。
この自己イメージは、「自己についての知識・記憶」であり、心理学で言うところの自己意識(鏡像としての自己)である。
それでは、哲学上の「自己意識(自分self)」を、どのように感知するか。
(基本テーゼ3)ひとは、対象に意識を向けたそのとき、「反射意識(意識の反作用がもたらす体感)」を得る。
この体感は、「自己意識(自分self)」の感覚(内包)を生み出す。
デカルトが「我思う」と言った瞬間に、「観察している我の感覚(内包)」が生まれる。
そして、デカルトが「故に、我あり」と言ったとき、我は、「自己意識(我)」を得たと感じる。
但し、その「自己意識(我)」は、「観察して得られた「我」ではない(意識の反作用の結果、得られた)」ので、
「姿・形(外延)」を欠いている。
即ち、「自己意識(我)」は、内包のみで、外延を欠いた「不完全な存在」である(我は、外延を欠いていることに気付かない)。
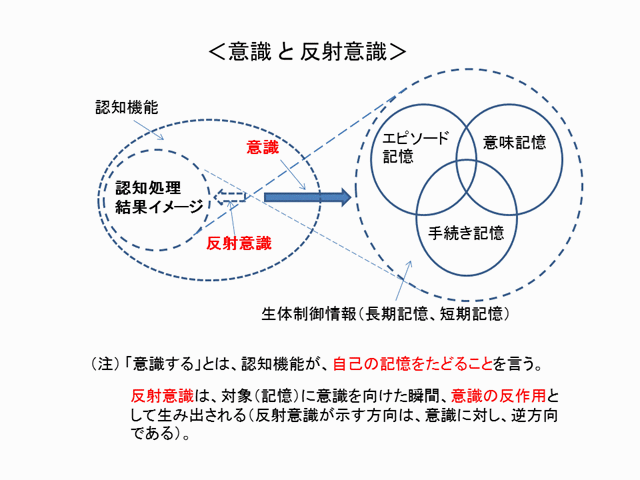
ひとは、内省的なとき、突然の「漠然とした不安」に襲われる場合がある。
それは、「自己意識(自分self)」の不完全な存在(外延を欠いていること)に関する無意識下の不安である。
(基本テーゼ4)ひとは、内なる情動(感情、欲望)を対象物に刻む(外化する)ことによって、自らの存在を確認しようとする。
基本テーゼ4においては、ひとは、「内なるものを、吐き出したい」という衝動に駆られる場合がある(芸術性の発露)。
また、ひとは、自らの存在を明らかにしてくれる「他者とのつながり(他者からの呼びかけ)」を、積極的に求める存在である。
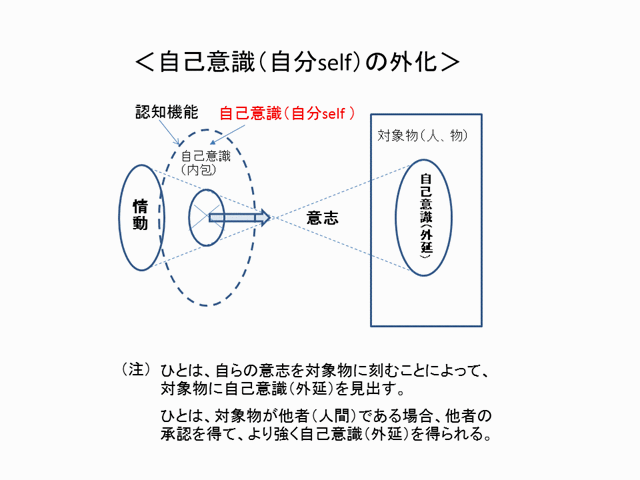
ひとは、如何に群れ社会の成員となりうるか。 それは、「わたし」であり、「あなた」となることを言う。
(基本テーゼ5)ひとは、「心(心の座)」を獲得して、群れ社会の成員たる資格「わたし」を得る。
ひとは、認知機能が自らの記憶をたどるとき、反射意識によって、思考の中心である「心(心の座)」の感覚(内包)を得る。
同時に、ひとは、この「心(心の座)」が自己を動かしている中枢であると感じる(社会的自己の発現)。
そして、この動かされている自己を、「わたし」と言い、同様に、「心(心の座)」を獲得した他者を、「あなた」と呼ぶ。
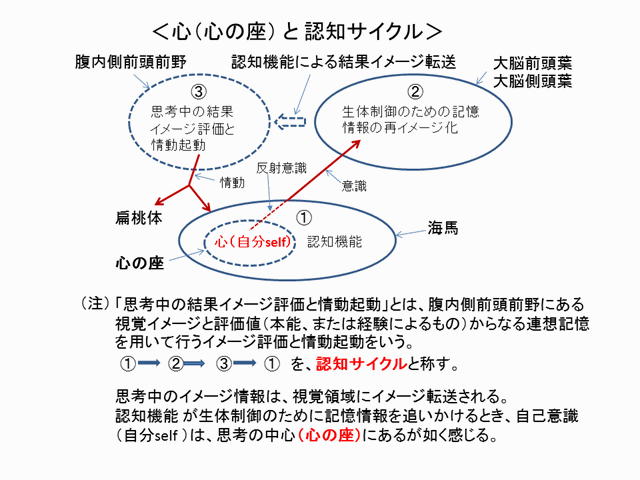
「わたし」と「あなた」の意志疎通は、どのように行われるか。
(基本テーゼ6)群れ社会成員間の意志疎通は、言葉または身体表現を使ったイメージ交換により行われる。
「わたし」と「あなた」は、互いに意思を表す言葉を連ねて、イメージを交換する。 その言葉(イメージ)の列は、
互いの頭脳に相手の意志(伝えたいイメージ)と情動の波を引き起こす(情動のハーモニーは、相互の信頼と愛を生み出す)。
「わたし」と「あなた」の意志疎通は、両者の共通事項(同じ言葉の使用、共通の利害、社会的立場など)によって、
親和度が変わる(親和度を高めるためには、互いに相手を許す心(寛容性)を持つことが重要である)。
「わたし」と「あなた」のより良き意志疎通を実現するためには、帰属する群れ社会のルールと価値観を共有し、
互いに共感する能力が求められる(互いに社会的立場の違いと情動を理解し、共感を深めるような言動<気遣い>が求められる)。
「わたし」と「あなた」の意志疎通は、人類にとって、どのような意味を持つか。
(基本テーゼ7)「わたし」と「あなた」の意志疎通は、互いの存在を確認し、互いを結びつける。
人類は、進化の過程で、同一種族の壁を乗り越え、個体(ひと)と個体(ひと)を結びつけ、
より大きい集団を維持する身体的能力(認知機能)を獲得した。
ただし、この能力を十分発揮するには、人類は多くの障害を乗り越えなければならない。
それは、
・人種間の外見上の差別感
・言葉の違いによる意思疎通の壁
・宗教の違いによる考え方の違い
などである。
これらの障害を乗り越えるためには、なによりも互いの違いを認め合う態度(寛容性)が重要である。
(参考)形而上学(アリストテレス)、方法序説・情念論(デカルト)、純粋理性批判(カント)、精神現象学(ヘーゲル)、
論理学研究(フッサール)、存在と無・嘔吐(サルトル)、善の研究(西田幾多郎)
社会脳仮説(Robin Dunber)、社会脳研究(Leslie Brothers)
3.人間は、「矛盾した存在」である(生存本能 と 群れ社会帰属)
一般市民社会では、あたりまえのことが、改めて掲げなければ、何事も始まらないということがある。
そこで、地球上で生きる人間の生命体としての本性(本能)を考察すれば、次のとおりであろう。
(テーゼ1) 人間は、個体として生き延び、自らの遺伝子をより多く残すよう定められている(生存本能)。
(テーゼ2) 人間は、個体として、より優位に生き延びるためには、群れ社会に帰属しなければならない。
「生存本能」があるということは、その個体が他の生命体と生存競争するということである。
仮に、同族内であっても、個体間の生存競争を生じる可能性を秘めている。
個体が、群れ社会に帰属するためには、その群れ社会内では、生存競争を抑制しなければならない。
一方、群れ社会が、その多様性(構成員の生態的多様性)を失えば、群れ社会そのものの存続が危うくなる。
すなわち、(テーゼ1)と(テーゼ2)とは、互いに矛盾する面を持っており、人間とは、そのような存在である。
4.人間は、「矛盾した存在」を、どのように克服しようとしているか(情動 と 認知機能)
人間は、個体として生まれ、群れ社会の中で生き延びるよう進化してきた。
人間は、互いに矛盾する個体としての生存本能(個性の主張)と群れ社会内での協調行動要請を、認知機能を使って調整し、
より大きい群れ社会に適応しようとしている。
(テーゼ3) 人間は、おのれの生存本能(個性の主張)を、「情動の表出」という形で他者に現わす。
(テーゼ4) 人間は、認知機能を働かせて、情動を抑制し、群れ社会の中で生きる術を獲得する。
小さな群れ社会(血族、同一種族)内では、「情動回路」の働きで、個性の主張(生存競争)と協調行動(共生)のバランスを取り易いが、
大きい群れ社会に順応するためには、「認知回路」を働かせる必要がある。
(参考)理化学研究所 RIKEN BSI NEWS No3 (情動のメカニズムの探求(二木宏明))
5.人間は、動物的本能に加え、新しい能力を身につけた(認知機能と生体制御モデル)
(テーゼ5) 認知機能とは、五感と過去の経験(生体制御情報)に基づいて、自己を制御する機能である。
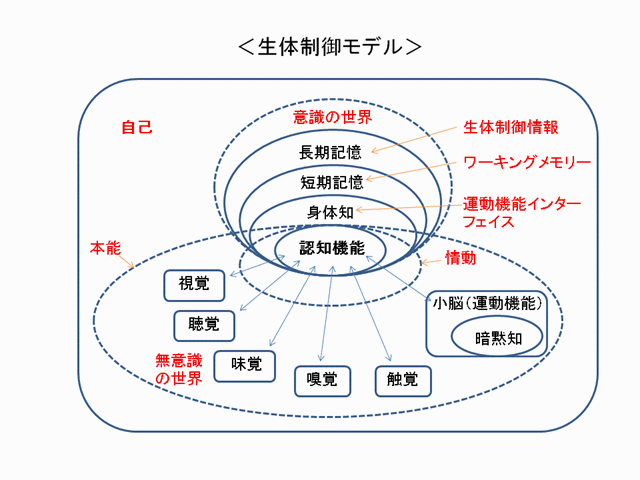
「暗黙知」とは、身体を動かす上で獲得された微妙な調整能力である(一般的に言われる暗黙知を狭義に捉え、身体調整機能のみに限定している)。
「身体知」とは、「自転車に乗る」等、一度獲得した能力が、その後も維持される場合の身体能力を言う(経験知一般ではなく、身体能力に限定している)。
「短期記憶」とは、五感から受け取った情報を認知処理した直後のイメージ(エピソード)で、短期的に保持されている記憶を言う。
「長期記憶」とは、短期記憶情報のうち、特に生体制御に必要であると情動に訴えるイメージと質感で、長期的に保持されている記憶を言う。
認知機能を理解するために、大脳各部位の働きの詳細を記述することは、大脳生理学の専門家にお任せして、読者のより理解あるコンピュータ分野の知識を借りて
説明する。
まず、生体制御機能を、コンピュータ処理モデルで表現するならば、次のとおりとなろう。
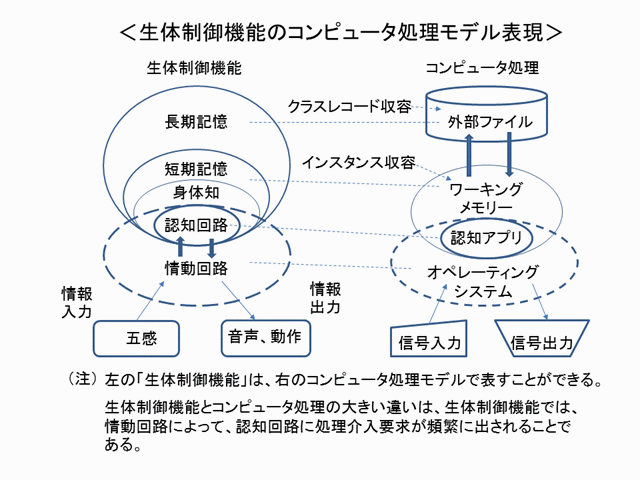
生体制御情報を解読しながら生体を制御することは、コンピュータ処理モデルの側からみれば、認知処理ソフト「認知アプリ」は、
インタープリタ型言語の性格を持っていると言える(このことは、生後取得した「言葉」によって、
生体制御情報を読み取り、自己を制御できることを意味する)。
「認知アプリ」は、外部ファイルにある生体制御情報(クラスレコード)を参照・解読しながら、自己制御信号を出力する。
「情動回路」は、五感によってもたらされる情報を調べて、その評価結果を「情動(感情、欲望)」という形で生成・表出する機能を持った大脳生理学上の
「回路」であり、それは、ある種のループ構造を持っている。
「認知回路」は、人類進化の過程で、情動回路を補完する機能として付加されたと思われる機能回路で、情動回路で自己の状況を評価できない場合に
機能する回路である。
それは、過去の経験から取得した生体制御情報(長期記憶)を用いて、自己の情動(感情、欲望)を満たす手段を見出す回路でもある。
この回路もまた、ある種のループ構造を持っている。
「認知回路」は、情動回路を補完する機能であるが故に、認知機能が生体制御情報を参照・解釈するたびに、情動回路による認知結果の評価を受ける。
それでは、情動回路による認知結果の評価は、何に基づいて行われるのだろうか。
(テーゼ6)情動回路による認知結果の評価値は、人類進化の過程で本能として獲得したもの、
または、誕生以来の経験(エピソード記憶)により、取得したもの(体験結果の特徴イメージと、
情動(欲求)を充足することが生体にとって有利不利、を連想記憶の形で保持)である。
コンピュータ・ソフトウエアの場合の条件分岐は論理関数(IF〜THEN〜)で行うが、生体制御による条件分岐(思考中の心的イメージの選択)は、
テーゼ6に言うところの「連想記憶上の評価値」を参照することによって行われる。
この「連想記憶」は、情動回路上の記憶で、認知回路上の記憶(長期記憶・短期記憶)とは記憶形式が異なり、
進化の過程でより早期に獲得した記憶機能(画像認識に特化した等:ニューラルネットで構成されている)で、捕食行動など本能的な行動を支えるために
獲得したものであると推察できる。
(参考)二重過程理論(Stanovich他)
6.人間(個体)は、群れ社会で学んだ知恵(経験)を、どのような形で身体に保持するか(生体制御情報の形式モデル)
生体制御情報は、短期記憶領域を経て、長期記憶領域(大脳前頭前野など)に蓄えられるが、具体的にどのような形で蓄えられるかは、
大脳生理学者にお任せするとして、著者なりに理解している生体制御情報の形式を、コンピュータ処理モデルで用いられる表現形式(リスト形式)で、
説明を試みたいと思う(これらの生体制御情報の形式は、ミンスキーの「フレーム」を参考に、筆者が考案したものである)。
(テーゼ7) 生体制御情報の形式は、意味記憶、手続き記憶、身体知、エピソード記憶の4形式に分類できる。
「意味記憶」とは、人または物の概念定義の記憶である。
一般的に、「手続き記憶とは、自転車の乗り方などの身体的な技能記憶を言う」とあるが、
身体的技能記憶は、論理的な思考を必要とせず、身体的技能に特化していることから、この仮説では、「身体知」として整理する。
そして、「論理的思考手続き記憶」を、この仮説では、改めて「手続き記憶」として整理する。
「エピソード記憶」とは、過去に認知処理したイベント(事象)のイメージ記録であり、そのうちの印象に残ったものが、
長期記憶として保存される(いわゆる、「思い出」である)。
意味記憶、手続き記憶、身体知、エピソード記憶の形式モデルを、順に図式で表す。
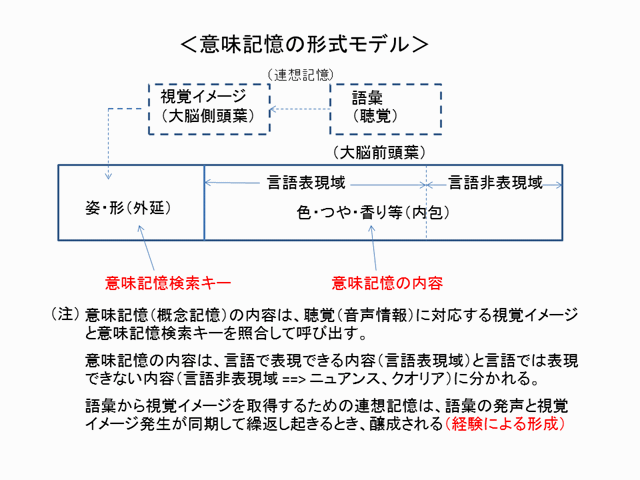
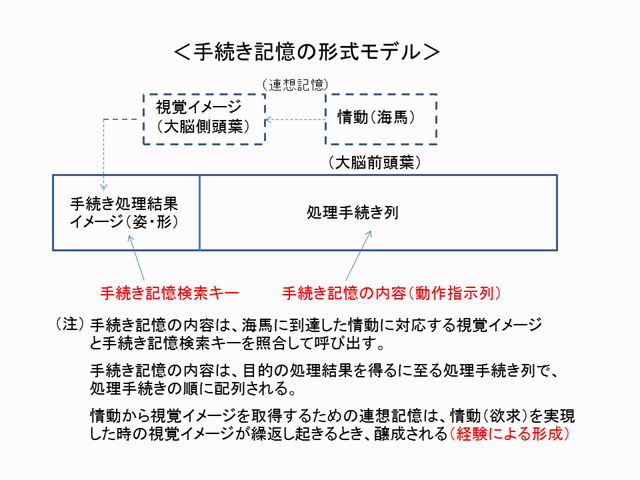
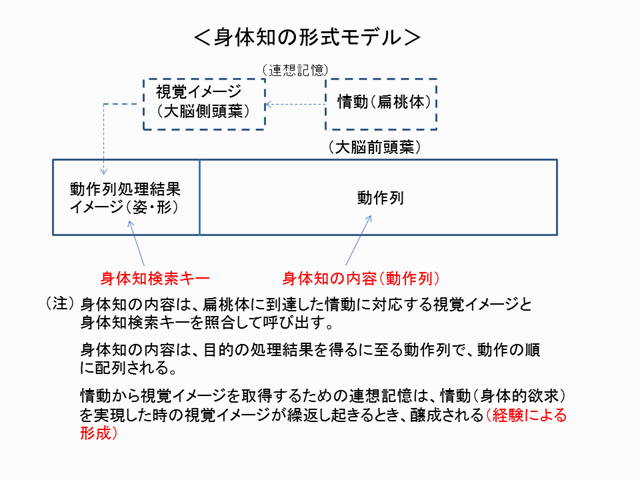
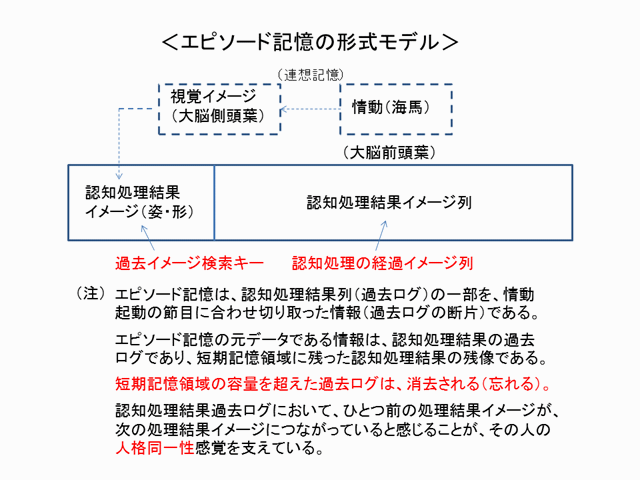
(参考)心の社会(Marvin Minsky)
7.人間(個体)は、生体制御情報を、どのように活用するか(デカルト以来の心身問題に対する一つの解答)
「ひと」は、生体制御情報を利用して、如何に自らの情動を満たそうとしているのだろうか。
「思考」は、どのようにして、情動を動かすか。
また、「情動」は、如何にして、「思考」に影響を与えるだろうか。
これらを説明するために、コンピュータ処理モデル表現を借りるならば、次の図のようになる。
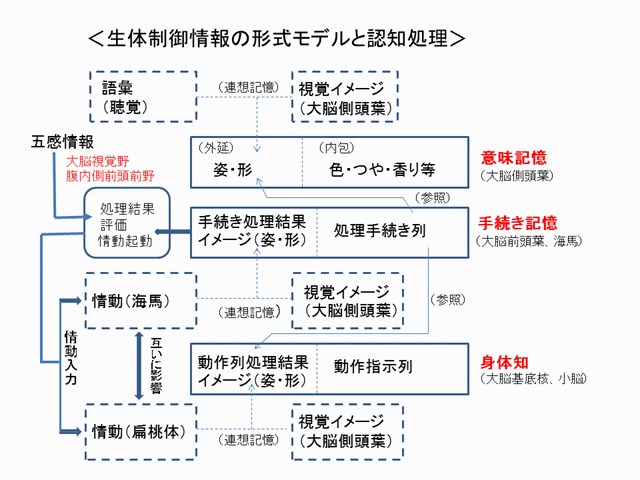
(テーゼ8) 「思考する」とは、認知機能が、情動回路によって示された与件(特徴イメージ)を満たす
過去の記憶を再生(心的イメージ化:視覚情報化)しながら、たどることをいう。
(テーゼ9) 生体は、五感情報が引き起こす情動(欲求)を情動回路で充足できない場合、
情動回路は、「本能または過去の処理結果イメージから造られたテーブル(連想記憶)」に記録されている
「過去の処理結果の特徴イメージ」を示して、「情動(欲求)を充足するであろう手続き記憶または身体知」が、
現在の記憶にあるかどうかを探すよう、認知機能(海馬)に働きかける。
認知機能は、求められた「手続き記憶(処理結果予想イメージ)」を検索(思考)し、その「有無」を返す。
情動回路は、有無を回答された「手続き記憶または身体知」を駆動することが
「生存するに有利か、不利か」を判断する。
この判断結果を受けて、情動回路は、「新しい情動(次の打つ手)」を海馬と扁桃体に送る。
(テーゼ10)海馬に届いた情動は、その情動を満たす過去のイメージを連想記憶で取り出し、
手続き記憶を起動(処理過程をイメージ化)する。
(テーゼ11)扁桃体に届いた情動は、その情動を満たす過去のイメージを、連想記憶で取り出し、身体知を起動する。
(テーゼ12)情動処理において、海馬と扁桃体は、互いに影響し合う(海馬は、扁桃体に対し抑制的に働き、
扁桃体は、海馬に対し機能強化に働く)。
このモデルにおいて重要なことは、思考の結果に伴う次の行動は、新しい情動という形で、海馬または扁桃体に「並行的に伝えられる」ことである。
すなわち、次なる身体行動の経過を自らの認知機能で確認できるし、また、その身体行動を中止することもできる。
生体(個体)存続を危うくするイメージは、次に予想される事態を回避するために、強い情動を引き起こし、海馬または扁桃体に素早い回避行動
を要請する(特に、本能的な回避行動を求められたときは、認知機能を経由せず、直接、身体知を起動する)。
この「強い情動(ストレス)」が繰り返されれば、海馬または扁桃体等に身体的障害(ダメージ)を引き起こす。
(参考)ソマティック・マーカー仮説(Damasio)
8.生命(ひと)は、「他者の世界」に生まれ、「ひと」になる(自我の成長、そして「自由」)
人間(個体)が、自然界に未成熟のまま生み出され、成熟を目指して懸命に生きてゆく様を、見ることができる。
「ひと」は、この姿を尊いものとして、自分自身を含め、ひと一人として害してはならないと思う。
(テーゼ13)「ひと」になるべき生命は、「他者の世界」に生まれ、他者から生きる術を学び、己のあるべき姿を求め成長する。
このテーゼは、「ひと」が「他者」に劣ることを意味しない(「ひと」の価値を決めるのは、「ひと」自身である)。
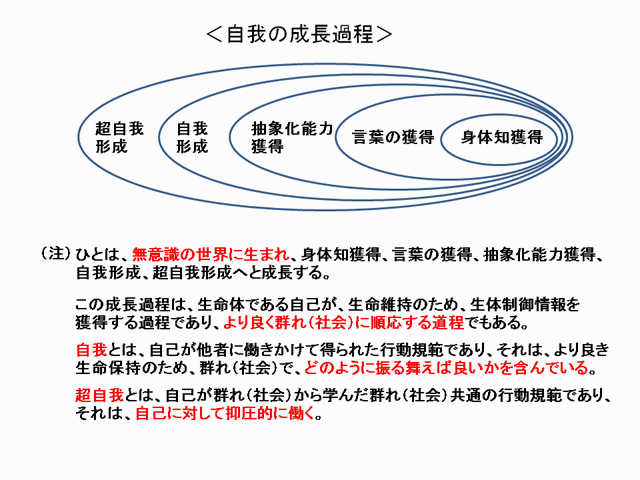
批判能力のない幼少期には、他者のメッセージを、無批判に受け入れがちである。
すなわち、他者から与えられる自己イメージが、そのまま、生体の制御情報として、記憶に取り込まれることを意味する。
生体(個体)が誕生後に後天的に獲得する認知能力によって、所与の自己イメージは修正されていく。 その段階を次図に示す。
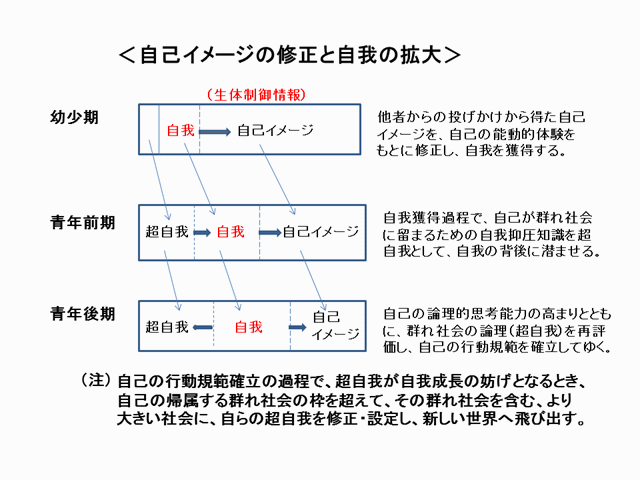
群れ社会内で「自由」を獲得することが、生体(個体)としての成長の原初的目標である。
なぜならば、生体(個体)は、群れ社会内で生存するために、他個体とともに生きてゆく能力を得る必要があり、
「ひと」と「他者」が、社会的(身分、所有関係等によって生ずる)制約なしに互いの生存を認め合う社会を、
目指しているからである。
(テーゼ14)「自由」とは、「超自我」の枠組みの中で、何の制約もなしに己の意志に従い行動できることを言う。
この「超自我」は、他者から与えられたものではなく、自ら会得した群れ社会内での行動規範であることに留意する。
この行動規範を超えた在り方を求められたとき、「不自由である」と感じる(人間は、自由の刑に処せられている:サルトル)。
9.生命(ひと)は、認知機能(理性)の衣をまとい、社会的存在になる(自己保存と自己疎外)
(テーゼ15)生命(ひと)は、認知機能(理性)の衣をまとい、社会的存在になる。
ここで言う「社会的存在」とは、群れ社会の中で自己と他者が互いに構成員として認め合う「生命(ひと)の有様」を言う。
そして、構成員(各個人)は、互いに他者から見れば、意志を持った実在者である。
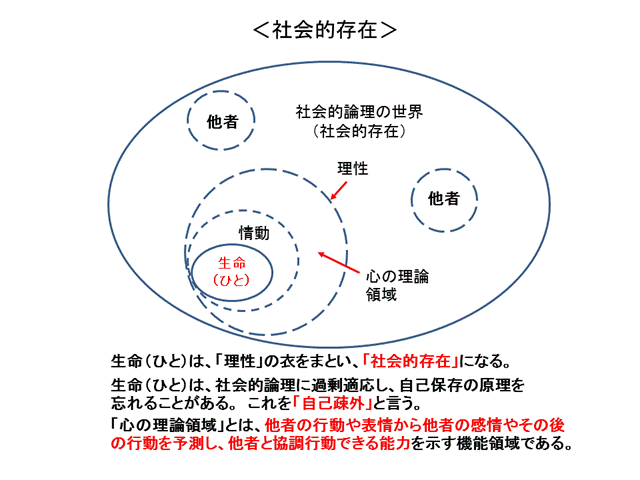
「ひと」になるべき生命は、己の成熟を目指して成長する過程で、様々な試練に出会う。 それは、
第一に、生物本来のもつ遺伝的特性(個性)、また、生まれ出た所の社会的環境(いわゆる、出自)によってもたらされる
生存のための初期条件の違いによってもたらされる試練であり、
第二に、「心の理論」の対象領域である対人関係経験則の取得と運用巧拙に伴う試練である。
そして、これらの試練を内に秘めながら、より良き成熟を目指し、生後に獲得した認知機能(理性)を働かせて、群れ社会に適応しようと努力する。
ここで言う「群れ社会」の範疇には、広く社会活動に伴うグループ(学校、企業、宗教団体など)を含む。
(テーゼ16)生命(ひと)は、群れ社会に過剰適応し、自己を見失う場合がある。これを「自己疎外」という。
自己保存の原理を忘れて、他者論理の大勢に従おうとする心または行為、或いは、確信もなく他者の論理に盲目的に従うこと
を「自己疎外」と言う(特に、宗教界に見られる非科学的教義に従うことは、厳に慎まなければならない)。
このとき、自己存在を確信させる他者の存在が、自己存在に置き換わった心の様態(憑依)を見ることができる。
(テーゼ17)生命(ひと)が群れ社会にうまく適応するには、「他者を助けて、自己を生かす道」を選ばなければならない。
群れ社会に生きるには、自己疎外に陥る可能性を排除し、常に自己保存の原理(生物としての自己保存本能)に忠実であり、
時には、所属する群れ社会を離れる勇気を持つ必要がある。
「ひと」にとって、どのような群れ社会に帰属するかは、「ひと」の自由と自己保存の根幹に関することである。
群れ社会が大きくなればなるほど、その中でより優位に生きようと、人間(個体)は、互いに大声で自己主張を繰り返し、徒党を組み、
「自己保存と自己疎外の相克」の状態に陥る(これを「煩悩の世界」という)。
残念ながら、筆者は、「煩悩の世界」で生きるための処方箋を知らない。ただ、「ひとの悪口を言わない」程度のことは分かる。
ここで、最近、目にとまった名言を披露したい。
”寒さにふるえた者ほど、太陽の暖かさを感じる
人生の悩みをくぐった者ほど、生命の尊さを知る”(ホイットマン)
(2016年8月 T.Kimura 記す)